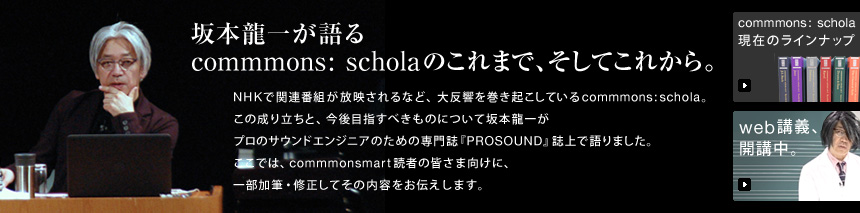HOME > commmons: schola > 【番外編】坂本龍一が語る commmons: scholaのこれまで、そしてこれから。
commmons:schola(コモンズスコラ)
schola
2010/09/17 UPDATE ![]()
小沼純一 :なぜ「schola」を始めたかと言いますと、現在、インターネットの普及により、誰もがあらゆる音楽情報に簡単にアクセスできるようになり音楽が世の中に溢れているわけです。ありとあらゆる音楽が無差別に並列された混沌の前に立たされることになりました。
坂本龍一 :スコラ(schola)とはラテン語でスクール「学校」という意味です。「音楽学」や、堅苦しい「音楽鑑賞」を強要しようというわけではありません。そういうものから自由になることを目指しているのです。自分だけの好みの世界に閉じこもるのでもなく、みんながゆるやかに共有できるスタンダード(標準)を作り直すことにより、音楽の歓びを、より広く、より深く共有することができたら素晴らしい。ここではポジティブに。勉強の楽しさを。
小沼 :私もおじさんですけど、(年配の者が若者に対して)「最近の若い者は、ロックなんて言ってるけど…」ジャズ好きの親父が「最近の若い者はマイルスも知らないで…」とか言うこともあります。過去を知らない(あるいは)わざと無視して、新しいことをやろうと考えたり、知った上で否定したり、ということはありました。今は逆に、多くの若い人は、(過去は)知らない、という状況があり、それがちょっと引っかかるんですね。
高橋悠治(※16) さんに「なんで知らなくちゃいけないのか?」ということを、尋ねたことがあるんです。悠治さんは、作曲家でありピアニストで、面白い本もいろいろ書かれたりしてます。ハーモニーの進行とか、規則っていろいろあるわけです。「知らなくたっていんじゃないか」という発想はもちろんあるわけですね。でもそこで「知っていると、それを使わないでいることができる」と。それは、はっと思ったんです。あっ、いいメロディー浮かんだ!?って口ずさんで、書いて、歌ったりするかもしれない。もしかしたらそれは誰かがずっと前に作ってるいかも知れないんです。本当はそれを知らなくて、自然に浮かんだりすることは、ちょっと才能があったりするのかもしれない。でも知っていたならば(他人からみれば)それはもうやられてることだし、ということになりますね。「知ってる」のと「知らない」のとは、どういうことなのかと改めて考えさせられたりしたのです。
坂本 :沢山のことを知ると(まだ)やられてないことは本当に少ない。
小沼 :そうなんですよね。
坂本 :やるべきことは残されているのか? 少なく見積もっても、判ってるだけでも、過去2000年くらいは音楽はあります。もっと言えば、そういうもの全部、知り尽くしているとしたら、僕たちに何ができるか?ということにもなってしまいます。知らないで、(これを作ったのは)自分なんだというのも恥ずかしい。
小沼 :ちょうど80年代には、もうすべてのことはやり尽くされてしまって、あとは、それをコラージュしていく。 ポストモダン(※17) として言われたんです。
坂本 :音楽だけでなく、建築、あらゆるメディアで(それを)言われた時代があった。ちょうどYMOが解散した後ぐらい(※18) からそうなってきて、もうすべてはできているので、あとは時代を飛び越えたいろんなスタイルをどう組み合わせるかというのがポストモダン。また、その時期も過ぎてしまって。今は何を作ったらよいか難しい時代なんですけど。
小沼 :今、私たちはインターネットでいろんなものを自由に聴くことができる。状況としては、ある種の歴史認識が失われてしまっている。逆にそれゆえに、ひとつのことには詳しいけど、すぐ隣で起こっていることは判らないという状況もあります。かつて、クラシック音楽というのは、いわゆるハイカルチャーという風に言われたわけです。でも、状況としてはクラシックもポピュラー音楽とは常に混じり合いながら、創造・享受されてきました。そうかと言って、同等だけども、価値とか、あるいは「いいもの」「つまらないもの」って当然あって、それはむしろ誰かが教えてくれるということでもあるかもしれないですが「自分で判断する耳」っていうのかな。そういうのが必要になってくるわけです。その時に、ひとつの判断基準、こういう風なものを積み重ねていったら自分でも感性とか知識が身につくかな。そういうようなものとして「schola」はあるんじゃないかな。
坂本 :今あるものは、実は今できたわけではなくて、何百年、何千年の積み重ねの上にできているんですね。ぼくも音楽を作っていますが、僕が発明した部分なんていうのは、ひとつの曲の中の5%もあればいい方です。95%くらいは人間が、集団的に積み重ねてきたものなんです。つまり和音、その上に乗っかるメロディーにしてもね。バッハの時代とそんなに変わってないんです。バッハでさえも、バッハひとりが作ったわけではなくて、その先人たちの何百年という積み重ねの上で仕事をしているにすぎないわけです。それはクラシック、ロック、ポップスに限らずどんなジャンルでもそう。先人がやったことを知る、その上で自分の個性とかやりたいことを作っていくのが一番いいのでしょう。
小沼 :今、1オクターヴ12個。この並びって、みなさん当たり前のように思ってるかもしれませんけど、とんでもないんですよね。
坂本 :オクターヴは振動数が倍になってるわけですね、これ(ラ♪)1秒間に440回振るえてるんですね。オクターヴ上は2倍で880。小数点も含めると物理的には無限の数値があるのに、人間はオクターヴの中を、5個とか7個とか12個とか、すごく荒い目安で音階を作ってるんです。いろいろ(スケールの)バリエーションがあるんですけど。700万年前とか、東アフリカの森林の中から、ホモサピアンスが進化してきたわけですけど、そんなに細かくしないでもすむ条件でこうなったというのが今の学説です。もしかしたら、ゴリラやチンパンジー、鳥なんか森という環境で生活しているわけで、水中に住むクジラ、もしかしたら、ぼくらよりずっと細かい目安で音を知覚しているかもしれない。12個しかないのでその組み合わせというのは、かなり限られてくる。だから100年前の曲と、今作られた曲が似ているということだってよくある。
小沼 :一本の弦があって、半分で区切るとオクターヴ、3分の2の長さで区切ると、五度、ソの音になりますね。
坂本 :オクターヴの発見、五度の発見というのは重要なことなんですね。つい4千年前の縄文人はぼくたちと同じ日本列島に暮らしていて、雷がなったら天の神様が怒っているとか、洪水になったら水の神様が怒っている、そういう風に感じてたと思うんです。音に対しても、音霊っていう言葉もありますけど、そういう感性を持っているわけですね。ある時、弦をちょうど真ん中を押さえたときに、共和する響きだと発見したときに、音の神話的な感受から、一種、数学的、物理的な感受の仕方、そこから操作へ、というのが始まるわけですね。
小沼 :そこからコンポーズするという意識が生まれてきたかもしれないですね。

坂本 :その前は実際、出土品からも出てるんですけど、鹿の骨などに穴を空けて、厳密に計って空けたのかもしれませんし、あるいは自然に空いている穴を利用した「石笛(※19) 」 (イワブエ)」。ピーッといろんな音が出るんですよ。例えば、海の神様に感謝を伝えたり、自分のためだったり。ユダヤ民族のが有名ですけど世界中の先住民族が持っていた「口琴 (※20) 」 。あれは自分のため、あるいは恋人に何か伝える。
小沼 :管とか竹とか、ひとつの音しか出ませんが、もうひとつあると、あるいは何人か別の人たちでもって交代でやると、メロディーという意識はないのかもしれないけど、コミュニケーションそのものにもありますね。
坂本 :これはね中央アフリカの(ピグミー(※21) の音楽♪)。素朴に聴こえますが、二人以上で決められたパターンでやってます。
小沼 :実は複雑になって洗練された音楽になってるんだけど、これが長いこと西洋人の目から見ると、劣っている音楽だったんですよね。
坂本 :そうなんですよね。この素晴らしさを西洋人は判らなかった(笑)。20世紀になって、やっとみんなこういうものの素晴らしさに気がつき出して、スティーヴ・ライヒ(※22) とかテリー・ライリー(※23) とかが、アフリカやアジアの音楽を勉強して、ミニマリズム(※24) のかっこいい(のを始めた)。ぼくが高校から大学に入る頃、こういうのが前衛だったんです。同じメロディーがずれていく、すると違うメロディーが聴こえてくる。こういうのが西洋音楽に…アフリカのピグミーから(すっ飛ばして)現代音楽に来ちゃったなあ(笑)。
小沼 :(はい。)西洋人からみると、ずっと西洋のクラシック音楽が一番素晴らしい音楽だとずっと思っていたのが、19世紀から20世紀にかけて、文化人類学、民俗学というのが発達して、自分たち以外の文化圏の音楽について関心を持ち出すわけですね。そのときには劣っていると多くの人は思っていた。だけど文化人類学、民族音楽学の成果として、今では、様々な音楽が認められて、どんな音楽もちゃんとひとつの価値を持っているというのが当たり前になりました。
小沼 :バッハにあるものが、クラシックでも現代音楽でも、様々なポピュラー音楽でも、使われている素材というのは、みんなもうバッハにある、そこにあるよ、ということなんですけど、いかがですか?
坂本:ジャズにしてもポップスにしても、ほぼありますね。アメリカのゴズペル(※25) なんかは、サブドミナントからドミナント、トニック (※26) にいくというのは、もろバッハに近いですね。ドミナントからサブドミナントにいく進行はないが。ロックでよく使う、いわゆる弱進行 (※27) は(クラシックの世界ではいけないというものですけど)、ないかな。バッハ以前というのが長いんです。バッハが亡くなったのが1750年、18世紀の真ん中。いわゆる古典派 (※28) 、ハイドン、モーツァルトとベートーヴェン、そういう時代に移り変わっていくところです。
小沼 : ハーモニー。時間軸に動かして和音を並べていく。規則がいっぱいあるんですよね。それが崩れていって現在になっていくわけですけど。

坂本 :アフリカの音楽にだって規則があるわけですけど、ヨーロッパではその当時、教会の権威が高かったので、音楽の専門家ではない宗教の権威の人たちが会議で、その当時のがんじがらめの規則を決めていったんでしょうね。ある間隔や規則で、これはいいとか。今聴くと、変に聴こえる、転調して聴こえるような。パラダイム (※29) という言葉を使いますけど、100年とか200年という意識されないレベルで、長い時間を支配する。ヨーロッパ音楽の歴史をみるとパラダイムが150年くらいで変わっていくんですね。ルネサンス (※30) が始まるのが、およそ1450年。バロック (※31) が始まるのが1600年、バッハが亡くなるのが1750年、150年足すと1900年、20世紀の初頭ですね。我々はまだそこの途中にいるのかもしれないですね。2050年くらいにまだぼくたちが知らない様式、規則だけでなく耳の喜びというか感性自体に変化が起きるのかもしれない。
小沼 :実はいろんな音楽があって、さっきのピグミーなんか聴いて、これは音楽なの?って思う人が居るかもしれない。ライヒなんかもそうですけど。私たちの耳、感性ってパラダイムというか、いろんな形で慣れているものに支配されてるんですね。自由だと思うとちょっと違いますね。
坂本 :音楽に限らず、日本では常識だと思っていることが、ほかの国、違う文化圏にいけば常識ではないっていうことは沢山ありますね。アラブ音楽なんかは、微分音=半音の間の音も認識しているんです。アラブ音楽の耳から比べると、モーツァルトのように1オクターヴの中に12音しか使ってない西洋音楽は、ものすごく単純に聴こえてしまうのです。
小沼 :バッハから150年、1900年くらいに、ドビュッシー (※32) 、ラヴェル (※33) が居て、ジャズも同じ時期なんです。そこが面白い。ドビュッシーの中でいろんな音楽の変化が起こった。産業革命 (※34) とか市民革命 (※35) とかあって、いろんな変化もあった。バッハの時代にもピアノはあったんですが、産業革命によって大きな鉄のフレームのピアノができたり、金管楽器もバルブの発明とか。そんな中でドビュッシーが出てくるわけです。印象派 (※36) なんかも。それまで画家は部屋の中で描いていたのが、外に出て描く。水か風とか、そういう動きとか。
坂本 :それまでは絵画の対象でなかったものが描かれていく。これも大きなパラダイム転換。産業革命によって変わった。楽器の改良によって音楽が変わってくるという面もありますね。音楽を作る人はガジェット (※37) 好き?(笑)
小沼 :それまでのヨーロッパっていうのは、イスラム圏なんかに比べると文化的には遅れていた。それが産業革命などで、デジタル化、数量化、つまり量を計る状況になりました。
(※16) 日本の作曲家、ピアニスト。1938年東京都生まれ。ピアノとコンピュータによる即興演奏や、日本の伝統楽器と声のための作曲、などの音楽活動を行っている。
(※17) 主に哲学・思想・文学・建築の分野で用いられた言葉。「モダン(近代)の次」という意味であり、モダニズム(近代主義)がその成立の条件を失った(と思われた)時代のこと。ポストモダニズム(Postmodernism)とは、そのような時代を背景として成立した、モダニズムを批判する文化上の運動で、近代の行詰りを克服しようとする動きのこと。
(※18)1983年ころのこと。
(※19) 古代の遺跡から穴の開いた石が発掘されることがあり、楽器ではないかという意見がある。人工的に穴が穿たれたもの、自然に穴の開いたものがあり、貫通型と非貫通型もある。大きいものは磐笛と書く。
(※20) 金属、あるいは竹でできた弁を有する楽器の一種。演奏者はこれを口にくわえるかまたは口にあてて固定し、その端を指で弾くまたは枠に付けられた紐を引くことによって弁を振動させて音を出す。
(※21) 人類学上、ピグミーとは特に身長の低い(平均1.5メートル未満)特徴を持つ、赤道付近の熱帯雨林に住む狩猟採集民であるとされてきた。ピグミーは中央アフリカ全体の熱帯雨林を生活拠点としている。
(※22) ミニマルミュージックを代表するアメリカの作曲家。ドイツ系ユダヤ人。フレーズの繰り返しを多用したり、ミニマリストであるという見方が一般的だが、純粋なミニマリストのスタイルには収まらない作品も多い。テクノミュージックやエレクトロニカのアーティストたちにも多大な影響を与えている。
(※23) アメリカ合衆国出身の作曲家。ミニマル音楽家の一人。現在ではインド歌唱及びピアノ独奏でも実演と教育を行っている。
(※24) 音楽においてはミニマル・ミュージックのこと。音の動きを最小限に抑え、パターン化された音型を反復させる音楽。1960年代から盛んになった。あくまで単純な反復のリズムがメインであり、曲として成り立つ最低限度に近いほど、展開も少ない。しかしそれらの中での微細な変化を聞き取るのが目的であり、全体的な視点から見れば決して無駄な反復ではなく、音楽は徐々に展開していると言える。 例として「ゴジラのテーマ」が挙げられる。
(※25) アメリカ発祥の音楽の一ジャンル。元来はキリスト教プロテスタント系の宗教音楽。ゴスペルは英語で福音および福音書の意。
(※26) あるスケール(音階)があったときに、スケールの最初の音を主音と言い、その音を中心とする(根音とする)和音を主和音(トニック)と呼ぶ。同じ要領でスケールの4番目の音は下属音でこの和音を下属和音(サブドミナント)。また、同じくスケールの5番目の音は属音(ぞくおん)と呼ばれ、この和音が属和音(ドミナント)となる。
(※27) 主音に対して、例えば5→4→3というように下がっていく進行のこと。
(※28) クラシック音楽の歴史において、一般に1730年代から1810年代頃まで続いた時期の芸術音楽の総称。代表的な作曲家として、ヨーゼフ・ハイドン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンなどが挙げられる。
commmons: scholaでは坂本龍一が選曲を担当。
(⇒詳細はこちら)
(※29) 一般用語としてのパラダイムは「規範」や「範例」を意味する単語であるが、科学史家トーマス・クーンの科学革命で提唱したパラダイム概念が、その意図からは誤解となるほどに拡大解釈されて一般化されて用いられ始めた。拡大解釈された「パラダイム」は「認識のしかた」や「考え方」、「常識」、「支配的な解釈」、「旧態依然とした考え方」などの意味合いで使われている。
(※30) 14世紀 - 16世紀にイタリアを中心に西欧で興った古典古代の文化を復興しようとする歴史的文化革命あるいは運動を指す。また、これらが興った時代を指すこともある。
(※31) 6世紀末から17世紀初頭にかけイタリアのローマ、マントヴァ、ヴェネツィア、フィレンツェで誕生し、ヨーロッパの大部分へと急速に広まった美術・文化の様式である。バロック芸術は秩序と運動の矛盾を超越するための大胆な試みとしてルネサンスの芸術運動の後に始まった。
(※32) フランスの作曲家。長音階・短音階以外の旋法の使用、機能和声にとらわれない自由な和声法などを行った。ドビュッシーの音楽は、代表作「海」や「夜想曲」などにみられる特徴的な作曲技法から、「印象主義音楽(印象派)」と称されることもある。
(※33) バレエ音楽『ボレロ』の作曲や、『展覧会の絵』のオーケストレーションでよく知られたフランスの作曲家。バスク系フランス人。
(※34) 18世紀から19世紀にかけて起こった工場制機械工業の導入による産業の変革と、それに伴う社会構造の変革のことである。市民革命とともに近代の幕開けを告げる出来事とされるが、近年では産業革命に代わり「工業化」という見方をする事が多い。
(※35) 封建的・絶対主義的国家体制を解体して、近代的市民社会をめざす革命を指す歴史用語である。一般的に、啓蒙思想に基づく、人権、政治参加権あるいは経済的自由を主張した「市民」が主体となって推し進めた革命と定義される。代表的なものは、イギリス革命(清教徒革命・名誉革命)、アメリカ独立革命、フランス革命など。この場合はフランス革命を指す。
(※36) 19世紀後半のフランスに発し、ヨーロッパやアメリカのみならず日本にまで波及した美術及び芸術の一大運動である。1874年にパリで行われたグループ展を契機に、多くの画家がこれに賛同して広まった。音楽史論では、19世紀末から20世紀初頭にかけての、ドビュッシーやラヴェルといった作曲家たちの音楽を「印象派」とすることが多い。
(※37) ガジェット(Gadget)とは、目新しい道具、面白い小物といった意味を持つ、携帯用の電子機器類を指す用語。特別な機能や実用目的を備えている道具で、通常の技術より変わっていたり独創的なデザインがなされたりする傾向にあるものを指す事が多い。